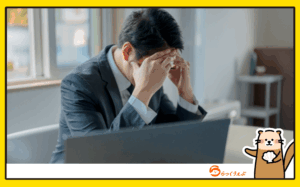訪問看護ステーションの立ち上げで必要なことは?手順や費用・助成金など解説

「訪問看護ステーションの立ち上げではどのような準備をすればいいの?」
「訪問看護ステーションの営業をスムーズに開始したい」
という方に向けて、本記事では訪問看護ステーションの立ち上げに必要な準備をまとめました。
開業にあたって注意すべき点も確認し、多くの方に愛される事業所を目指しましょう。
訪問看護ステーションの需要は高い?

高齢化の進展により、訪問看護ステーションの需要は年々高まっています。病院ではなく自宅で療養を続けたいと望む方には、訪問看護ステーションが選ばれるでしょう。
また、訪問看護ステーションは、入院病床数を削減し、医療費を抑制する上でも社会的にも医療的にも重要な役割を担っています。
国が進める医療費抑制政策でも在宅医療が推進されており、今後も訪問看護ステーションの存在意義は拡大していくと予想できます。
訪問看護ステーションの立ち上げ手順

- コンセプト・サービス内容確定
- 法人の設立
- 事業計画書の作成
- 物件取得
- オープニングスタッフの確保
- 備品などの調達
- 指定申請
訪問看護ステーションの立ち上げは、上記の手順で進めるとスムーズです。それぞれ詳しくみていきましょう。
1.コンセプト・サービス内容確定
訪問看護ステーションを立ち上げる際は、最初にコンセプトとサービス内容を明確にしましょう。
対象とするエリアの利用者層・競合の情報を調べてコンセプトを定めてから、提供するサービス内容を決めると地域のニーズに合った運営が可能です。
また、コンセプトは独自性が強く、具体的なものを定めましょう。たとえば、がんの在宅ケアに力を入れるため「がん看護専門看護師」の資格を持つスタッフを揃えると、地域のがん患者のケアをコンセプトとした訪問看護ステーションになります。
利用者のニーズに沿っていて競合にはないコンセプトを決めると、差別化が進められて地域の利用者獲得につながるでしょう。
2.法人の設立
訪問看護ステーションを開設するには法人格の取得が必須であるため、株式会社・合同会社・医療法人など、目的や規模に合った法人形態を選んで申請しましょう。
法人格を持たない場合、介護保険や医療保険の指定認定を受けられず、正式な訪問看護事業所として運営できません。
各法人の種類に沿った要件を整え、登記申請や定款の作成などをしましょう。
3.事業計画書の作成
訪問看護ステーションを立ち上げる際には、事業計画書の作成をしましょう。事業計画書には、対象とする地域・利用者層・サービス内容・運営方針などの事業に関わる内容を明確に示します。
初期費用や運転資金、収益予測を具体的に数値化し、資金繰りをシミュレーションしておきましょう。
特に訪問看護ステーションの主な収益となる介護報酬や診療報酬は、入金までにタイムラグがあるため、それを考慮した具体的な資金繰りは事業計画書に盛り込むべき内容です。
金融機関や日本政策金融公庫から融資を受ける際も事業計画書が審査の基準となる場合が多く、資金調達にもつながります。
4.物件取得
訪問看護ステーションを立ち上げる事業計画がフィックスしたら、スタッフの待機場所となる事務所を取得しましょう。
訪問看護ステーションの事務所は「事務所としての専用区画があること」や「事業の運営に必要な広さがあること」「相談等に対応できる適切なスペースがあること」が設備基準で定められています。
そのほか、自治体によっては独自に基準を設けている場合があるため、必ず自治体に確認しながら物件の契約を進めましょう。
駐車場や駐輪場の有無、交通アクセスなどにも注目し、事業内容に沿ったサービスが展開できる物件を探す必要があります。
訪問看護ステーションの立ち上げ費用について詳しくはこちら↓
訪問看護ステーションの立ち上げに必要な費用|詳しい内訳や調達方法などの紹介
5.オープニングスタッフの確保
- 保健師・看護師又は准看護師を常勤換算方法にて2.5名以上配置する
- 上記の保健師・看護師又は准看護師のうち1名は常勤である
- 保健師又は看護師である管理者を1名配置する
- 理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士を実情に応じた適当数を配置する
都道府県などから指定受けた訪問看護ステーションを開業するには、上記の人員基準を満たしてオープニングスタッフを集める必要があります。
これらの基準を満たしたうえで事務職員を採用すれば、開業後にスムーズな運営が可能です。
また、研修や教育体制を準備しておけば、開業後から質の高いケアを提供しやすくなります。
業界で人材が不足している現状から「求人サイトへの掲載」「独自の採用ページの作成」など、複数の方法を組み合わせて募集すると、多くの人の目につきやすくなるため有効です。
訪問看護ステーションの人員基準について詳しくはこちら↓
訪問看護ステーションの立ち上げに必要な人員基準|常勤換算や違反時の処分など解説
6.備品などの調達
訪問看護ステーションでは、血圧計やパルスオキシメーターなどの医療機器や衛生用の消耗品などの備品が必要です。
訪問に使う車や自転車も確保しておきましょう。
新品だけではなくリースや中古品を取り入れれば、初期費用を抑えながら必要な備品を揃えられます。
7.指定申請
訪問看護ステーションを開設するには、都道府県や市区町村に申請し、事業所として指定を受けなければなりません。
指定が受けられると、介護保険や医療保険を使った報酬の請求が可能になります。
必要な手続きは自治体ごとに異なるため、開業する地域の自治体に確認して準備を整えましょう。また、実際に事業所が基準を満たしているかを確認するための実地調査が行われる場合もあります。
訪問看護ステーションの立ち上げ後に必要なこと

- 請求のタイムラグを加味した資金繰り
- 人材の確保と育成
- 地域連携と広報活動
訪問看護ステーションの立ち上げ後は、上記の3点が特に重要となるポイントです。
訪問看護ステーションの立ち上げに失敗しないポイントについて詳しくはこちら↓
訪問看護ステーションの立ち上げは失敗しやすい?主な原因や成功のポイント
請求のタイムラグを加味した資金繰り
訪問看護ステーションの主な収益である診療報酬や介護報酬は、サービスを提供してから2~3か月後に入金されます。
その間も人件費や家賃、備品費などの支払いは続くため、資金に余裕がないと運営が不安定になるでしょう。
特に開業直後は収入が少ない期間が続くため、事前に入念な資金計画を立てたうえで数か月分の運転資金を準備しておかなければなりません。
また、請求業務には専門知識が求められるうえ、自社で処理すると負担が大きくなります。介護事務代行サービスを利用すれば、複雑な手続きのアウトソーシング化が可能です。
介護事務代行について詳しくはこちら↓
介護事務代行とは?メリット・デメリットや選び方、主な代行業者などを解説
人材の確保と育成
訪問看護ステーションの運営を安定させるうえで、スタッフの確保や育成、定着は重要です。開業時に人員基準を満たしていても、離職やシフトの調整などで人手不足に陥る可能性があります。
特に看護師やリハビリ専門職は慢性的に不足しているため、求人活動を継続的に行うことになるでしょう。
ホームページに採用ページを作成しておくと、定期的な募集が可能です。また、研修や勉強会を通じてスキルアップを図り、採用したスタッフを早めに戦力とする教育体制をつくりましょう。
スタッフの定着を図るには、定期的な業務の見直しやフローの再確認が有効です。効率的な運営によって一人あたりの業務量を見直し、スタッフの負担を減らすよう努めましょう。
地域連携と広報活動
訪問看護ステーションの利用者を増やすためには、地域と連携体制を構築しておく必要があります。
病院やクリニック・介護事業所などと積極的に交流し、スムーズなケアや重複・漏れのないサービスを提供しましょう。
また、地域包括支援センターやケアマネジャーと信頼関係を築くと、新規利用者を優先的に紹介してもらえる可能性が高まります。
地域連携と並行して、広報活動にも力を入れましょう。広報活動には、ホームページの作成が必須です。
今は高齢者でもスマホを使う時代であり、訪問看護ステーションを探す人のほとんどはホームページを確認しています。
利用者を紹介してくれる病院関係者やケアマネジャーなども、ホームページを見る可能性が高いため、事業所の強みや特徴を分かりやすく掲載しておきましょう。
また、ポスティングDMやパンフレットの配布など紙媒体での広報活動も、地域での認知度向上に効果的です。
訪問看護ステーションのホームページ作成について詳しくはこちら↓
訪問看護ステーションのホームページ作成がもたらす効果や作り方のポイント
訪問看護ステーションを立ち上げる際に注意すべきこと

- 物件は契約前に自治体の担当課へ相談
- 助成金や補助金の適切な活用
- 管理者の条件を確認する
訪問看護ステーションを立ち上げる際には、上記3点に注意してください。それぞれ詳しくみていきましょう。
物件は契約前に自治体の担当課へ相談
訪問看護ステーションでは、物件を契約する前に必ず自治体の担当課へ相談しましょう。物件の位置や面積、設備条件によっては指定基準を満たせないおそれがあります。
自治体に確認せずに契約すると、後日基準を満たせない物件だと発覚しても修正のしようがなく、開業できない事態に陥るかもしれません。
助成金や補助金の適切な活用
国や地方自治体は、訪問看護ステーションをはじめとする事業を推進するためにさまざまな助成金や補助金を提供しています。
助成金や補助金を活用すると、開業資金や運転資金の不足分を補えたり、資金繰りの支えになったりするでしょう。
助成金や補助金は事業の目的や条件に応じて多様な種類があり、それぞれ申請期限や対象要件が細かく設定されています。
自己資金だけで開業や運営の安定化を図るには大きなリスクが伴うため、利用できる助成金や補助金について情報収集を進めて計画的に資金調達を行いましょう。
訪問看護ステーションの立ち上げで使える助成金や補助金について詳しくはこちら↓
訪問看護ステーションの立ち上げ時に役立つ助成金や補助金を紹介
管理者の条件を確認する
- 看護師
- 保健師
- 助産師
訪問看護ステーションの管理者は、上記3つのうちいずれかの資格を所有している必要があります。また、専従かつ常勤で勤務できる人材でなければなりません。
さらに、在宅医療に関する知識と経験を備えていることが管理者としてふさわしいとされています。
開設者が無資格の場合は管理者候補を早めに決め、必要に応じて研修や学習の機会を設けるのが望ましいでしょう。
訪問看護ステーションの管理者の条件について詳しくはこちら↓
参考:訪問看護ステーションの立ち上げに欠かせない資格や管理者の条件など解説
訪問看護ステーションのホームページ作成はらっくうぇぶへ

訪問看護ステーションのホームページを作成するなら、ぜひらっくうぇぶにおまかせください。
らっくうぇぶは、介護業界専門のホームページ作成代行であり、事業所の強みや特徴を分かりやすく伝えます。
また「月々3,800円 (税込4,180円 )からホームページが持てる」月額制のサービスです。初期費用が必要ないため、開業資金に余裕がない場合でも利用しやすいでしょう。
介護施設経営での高い実績も兼ね備えているためWEBに関する業務だけではなく、介護業界特有のお悩みもご相談いただけます。
訪問看護ステーションのホームページ作成でお困りの方は、らっくうぇぶまでお気軽にお問い合わせください。
訪問看護ステーションの立ち上げ準備を漏れなくしておこう

訪問看護ステーションを開設するには、法人格の取得や人員基準の確保などの基本基準を押さえる必要があります。法律で規定されている運営基準を満たしていないと、開業はできないため、すべての基準をクリアしておきましょう。
地域との連携や広報活動も早めに進めておけば、開業後の利用者獲得につながります。また、広報活動において、ホームページの作成は必須です。
訪問看護ステーションの開業準備に追われて時間がない場合には、ホームページ作成代行に依頼するのもよいでしょう。
らっくうぇぶは、介護業界に特化したホームページ作成代行サービスで、事業所の強みや特徴を伝えるホームページの作成が可能です。
ホームページでは、訪問看護ステーションを必要とする方だけではなく、公共施設・地域包括支援センター・ケアマネジャーなどにも事業所の存在をアピールできます。
事業所の強みや特徴をホームページで伝えられれば、多くの利用者を紹介してもらいやすくなるでしょう。
気になった方は、ぜひ以下のリンクより「らっくうぇぶ」の詳細をご確認ください。

カテゴリー|立ち上げ