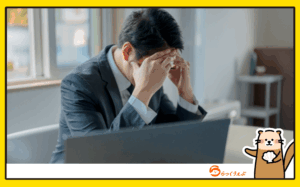訪問看護ステーションの立ち上げに欠かせない資格や管理者の条件など解説
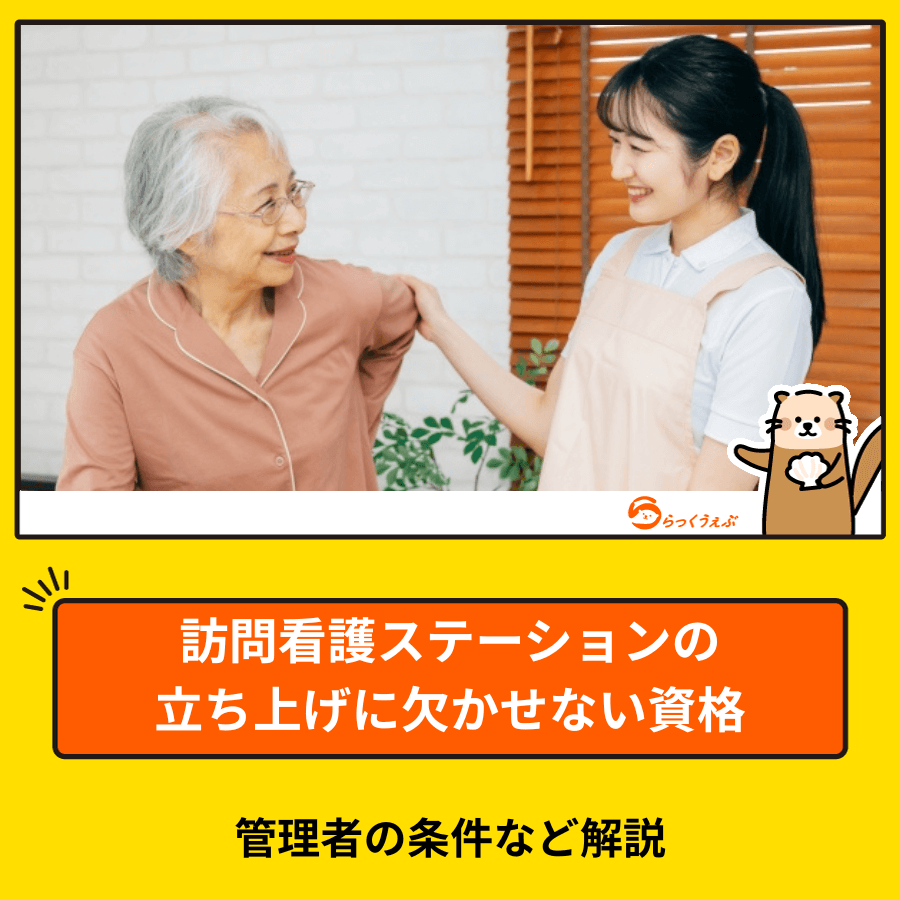
「訪問看護ステーションを立ち上げる際にはどんな資格が必要なの?」
「訪問看護ステーションの管理者になる条件は?」
訪問看護ステーションを開業しようと考えている方のなかには、上記のような疑問をお持ちの方もいるかと思います。
本記事では、訪問看護ステーションの立ち上げに必要な資格や管理者の条件などを紹介します。
訪問看護ステーションの立ち上げに必要な資格
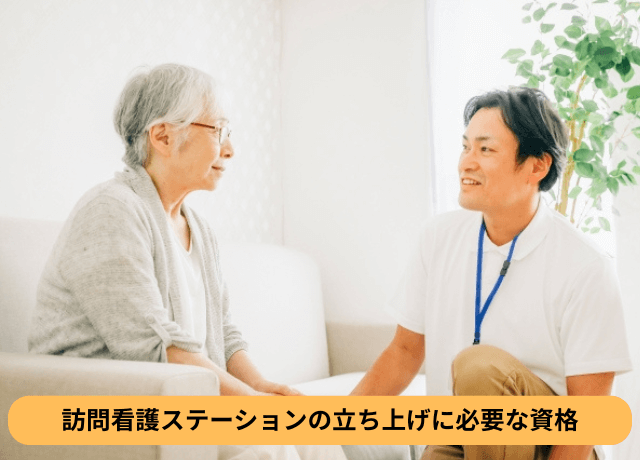
訪問看護ステーションを立ち上げる際に、管理者や経営者が保有しておかなければならない資格に関して紹介します。
管理者が必要な資格
- 看護師
- 保健師
- 助産師
訪問看護ステーションの管理者は、上記3つのうちいずれかを保有しておかなければなりません。
准看護師の資格では管理者にはなれないため、注意しましょう。
自身で上記の資格を持っていない場合には、資格保有者を探して管理者とする必要があります。
経営者は無資格でも問題ない
経営者は、看護師などの資格を保有していなくても問題ありません。
現場に入らずに、経営に専念する人員を経営者に登用することも可能です。
経営の知識や経験が豊富な人員が参画する予定であれば、経営者になってもらうとよいでしょう。
ただし、多くの訪問看護ステーションでは管理者が経営者を兼任しています。
訪問看護ステーションの管理者に求められる資格以外の条件

- 医療機関で一定期間以上経験がある
- 専従・常勤
- 関連機関の研修を受講
上記3つの条件が、訪問看護ステーションの管理者には求められます。
管理者に必要な資格以外の条件に関して、詳しくみていきましょう。
医療機関で一定期間以上経験がある
訪問看護ステーションの管理者に関して、厚生労働省は上記の実務条件を設けています。
医療機関での看護や訪問看護などの業務を一定期間行った経験がなければ、訪問看護ステーションの管理者に就くことはできません。
条件に明確な期間は定められていませんが、事業申請の際に経歴を確認される場合があるため、一定以上の経験が必要です。
引用元:厚生労働省|指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について
専従・常勤
管理者は、開業後に訪問看護ステーションへの専従・常勤が必要です。厚生労働省の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」では、上記のように定められています。
ただし、2024年度に診療報酬が改定された際、管理上支障がなければ他の事業所でも業務ができると定められました。同一法人であれば、複数の事業所での兼務が可能です。
引用元:厚生労働省|「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について
関連機関の研修を受講
厚生労働省は上記の条件を設けているため、管理者は関連機関の研修を受講して訪問看護の知識をつける必要があります。
訪問看護ステーションの管理者を対象とした研修は、各都道府県や全国訪問看護事業協会など訪問看護関連の団体などが実施中です。
経験などに応じて受講し、管理者としての資質を確保・維持しましょう。
引用元:厚生労働省|指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について
訪問看護ステーションの従業員に必要な資格

- 保健師、看護師または准看護師(看護職員):常勤換算で2.5人以上の員数を確保し、うち1名は常勤であること
- 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士:指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
訪問看護ステーションの従業員には、上記の人員が必要と定められています。
保健師、看護師または准看護師(看護職員)の2.5人は、常勤の人員を1人と換算して数えましょう。常勤の人員の所定労働時間が週40時間の場合、週20時間程度勤務する非常勤の人員1人につき0.5人と数えます。
参考:厚生労働省|社会保障審議会介護給付費分科会(第220回)資料3 訪問看護
訪問看護ステーションの管理者が行う主な業務

- 事業所の運営と経営管理
- 従業員のマネジメントと教育
- サービスの質向上と管理
- 地域連携と多職種連携
訪問看護ステーションの管理者の業務内容は、主に上記の4つです。それぞれ詳しくみていきましょう。
事業所の運営と経営管理
- 事業計画の実行
- 適切な人員配置
- 設備や備品管理
- 広報活動
- 各種マニュアルや規定整備
- 行政対応
事業所の運営と経営管理に関する管理者の業務は、主に上記の6つです。
訪問看護ステーションの事業計画を滞りなく実行し、定められた基準に基づいて適切に人員配置や設備・備品管理を行わなければなりません。
また、ホームページの開設やケアマネジャーへの営業など、認知してもらうための広報活動も実施しましょう。
一貫したサービスの提供や安全確保などのため、各種マニュアルや規定も整備が必要です。
行政機関から「指定」を受けたり定期的な更新審査を受けたりしなければならないほか、地域包括ケアシステムと連携することも重要であることから、密接な行政対応も必須となります。
従業員のマネジメントと教育
- スタッフの育成・評価
- モチベ-ション管理
- コミュニケーション促進
- 勤怠管理
従業員のマネジメントや教育に関する業務は、主に上記の4つです。
同行訪問やシャドウイング・研修のセッティングなどで従業員を育成し、従業員ひとりひとりのキャリアプランや習熟度に合わせて定期的な評価・フィードバックを行いましょう。
モチベーションの向上や従業員同士のコミュニケーション促進に努めれば、連携が行き届いた高品質なサービスが提供可能です。
また、従業員の健康や生産性、組織全体の健全性などを維持するため、適切な勤怠管理も欠かせません。
サービスの質向上と管理
「必要なシステムの導入」「従業員間の情報共有の迅速化」等により、サービスの質を向上させて、事業を管理しましょう。
サービスが向上して管理体制が整うと、利用者の満足度や安全性が向上します。
地域での信頼獲得や利用者の増加につながるため、事業を長期的に継続するうえで重要な業務です。
地域連携と多職種連携
- 医療機関との連携強化
- ケアマネジャーとの関係構築
- 地域ネットワークへの参画
地域連携と多職種連携に関する業務は、主に上記の3つです。
医療機関やケアマネジャーは、訪問看護を必要とする後期高齢者とのつながりを多く持っています。
こまめに営業をかけ、訪問看護ステーションの強みや特徴を医療機関やケアマネジャーへ伝えましょう。
訪問看護ステーションのホームページ作成はらっくうぇぶへ
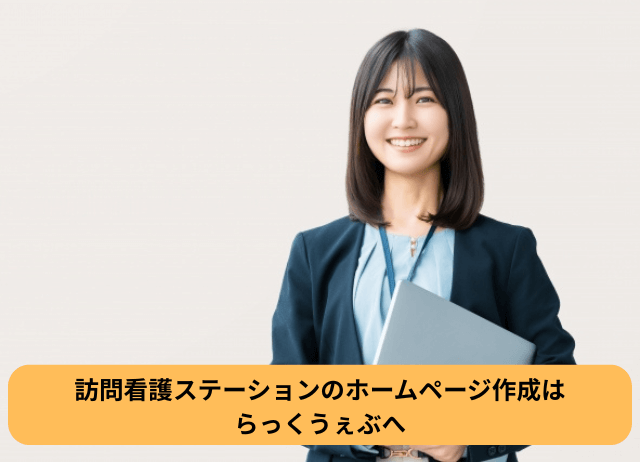
訪問看護ステーションの利用者を獲得するため、立ち上げ前にホームページを作成しておくことをおすすめします。
今は高齢者でも、スマホを持つ時代です。訪問看護を必要とする方やその家族は、ほぼ確実にホームページを見て利用する事業所を決めるでしょう。
開業準備に追われ「ホームページまで手が回らない…」と考えている方は、ぜひらっくうぇぶにおまかせください。
らっくうぇぶは、介護業界専門のホームページ作成代行であり、事業所の強みや特徴を伝えるホームページを月額3,800円+税で提供しています。
ホームページの作成や運営をアウトソーシング化すれば、業務の効率化や作業負担の軽減にもつながるでしょう。
訪問看護ステーションのホームページ作成は、ぜひらっくうぇぶにご相談ください。
訪問看護ステーションの立ち上げ時に必要な資格を知っておこう
訪問看護ステーションの管理者は、看護師・保健師・助産師のうちいずれかの資格を保有しておかなければなりません。
他にも管理者には「医療機関で一定期間以上経験がある」「専従・常勤である」「関連機関の研修を受講している」などの要件が必要です。
立ち上げ時に管理者となる人は、管理者としての要件を満たしているかを確認しましょう。
また、訪問看護ステーションの立ち上げ前には、ホームページの作成も並行してプランニングすることがおすすめです。
開業準備で忙しい場合には、ホームページ作成代行を利用しましょう。
らっくうぇぶは、介護業界に特化したホームページ作成代行サービスです。
複数店舗のデイサービス運営実績を活かし、訪問看護ステーションの強みや特徴が伝わるホームページを作成します。
気になった方は、ぜひ以下のリンクより「らっくうぇぶ」の詳細をご確認ください。

カテゴリー|立ち上げ