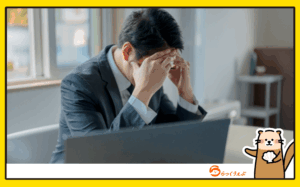みなし訪問看護とは?訪問看護ステーションとの違いやメリットデメリットなど
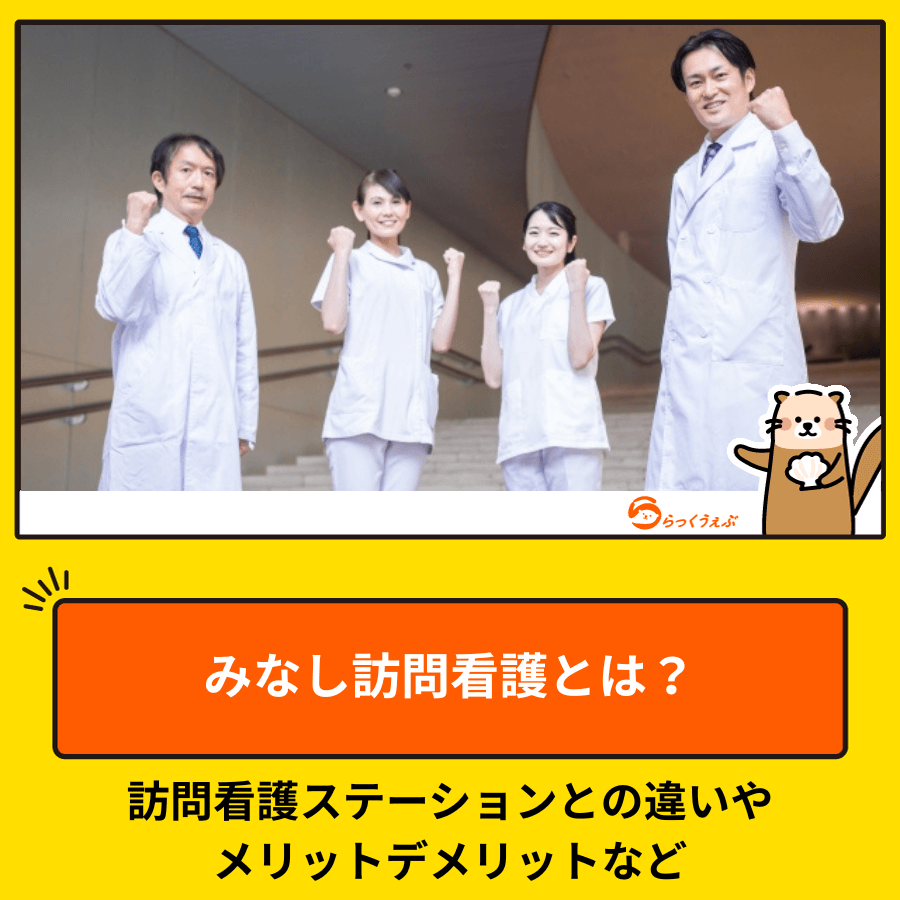
「みなし訪問看護って何?」
「みなし訪問看護と訪問看護ステーションはどうちがうの?」
みなし訪問看護を開業予定の方は、上記の疑問を抱えているかもしれません。
在宅医療の需要が高まるなか、病院や診療所が参入しやすい仕組みとして、みなし訪問看護が注目されています。
ただし、サービスの提供に制限があるため、開業前に正しく理解して適切な運営につなげましょう。
本記事では、みなし訪問看護の詳細や訪問看護ステーションとの違いなどを紹介します。
みなし訪問看護とは
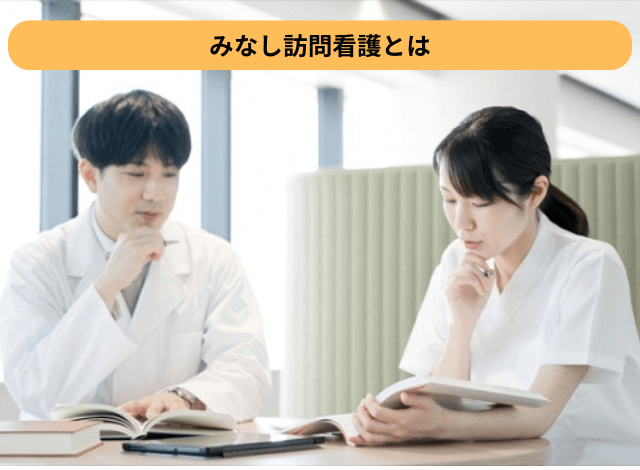
みなし訪問看護とは、病院や診療所が自院の一部として訪問看護を提供する仕組みです。
通常の訪問看護ステーションと同様に、患者の自宅に看護師を派遣し、医師の指示に基づいて処置や支援を行います。
また、診療所や病院に併設する形で訪問看護を行うため、比較的立ち上げやすいのが特徴です。
みなし訪問看護と訪問看護ステーションの違い
| みなし訪問看護 | 訪問看護ステーション | |
|---|---|---|
| 運営母体 | 病院や診療所などの医療機関 | 訪問看護サービスを専門に行う事業所 |
| 指定 | 新たな指定申請は必要なし | 指定を受ける必要あり |
| 対象者 | 自院の患者 | 地域で訪問看護を必要とする幅広い利用者 |
| サービス内容 | 自院が提供する診療科の範囲内でケア | 多様なニーズに対応 |
| 人員配置基準 | 適当数 | 専従の看護職員を常勤換算で2.5人以上配置 |
みなし訪問看護と訪問看護ステーションの主な違いを、上記にまとめました。それぞれの違いを詳しくみていきましょう。
運営母体・指定
みなし訪問看護は、病院や診療所など既存の医療機関が母体となり自院の機能を活かして展開するサービスです。地方自治体または地方厚生(支)局長から指定を受ける必要がなく、既存の診療体制に組み込んで訪問看護を提供できます。
開業手続きを簡略化でき、初期投資の負担を抑えやすいため、在宅医療へ参入しやすい点が特徴です。
一方、訪問看護ステーションは地方自治体から指定を受けた「指定訪問看護事業所」として、独立して運営されます。
医療機関から独立しているため、地域全体を対象に幅広いサービスを提供できますが、開業準備や人員確保などが比較的困難です。
サービス内容・対象者
みなし訪問看護は、運営母体の病院や診療所の患者を対象に運営母体の診療科に関するケアに基づいてサービスが提供されます。
訪問看護ステーションは地域全体の住民を対象とし、診療科に関わらず幅広いニーズに対応可能です。地域の医療機関などと連携しながら、多様なケアを提供できます。
人員配置基準
みなし訪問看護では、運営する病院や診療所が既存のスタッフを活用してサービスの提供が可能です。人員配置基準は「保健師、看護師又は准看護師を適当数配置していること」と定められています。
みなし訪問看護に専従する常勤看護師を確保する必要はなく、運営元である病院や診療所の外来や病棟勤務と兼務できます。
訪問看護ステーションは、常勤換算で2.5人以上の専従する看護職員の配置が必要です。人件費や採用コストは、大きな負担となるでしょう。
訪問看護ステーションの人員基準について詳しくはこちら↓
訪問看護ステーションの立ち上げに必要な人員基準|常勤換算や違反時の処分など解説
みなし訪問看護のメリット

- 立ち上げが容易
- 医師との連携が密
- 継続的な支援が可能
- 利用者を獲得しやすい
みなし訪問看護のメリットは、主に上記の4点です。それぞれ詳しくみていきましょう。
立ち上げが容易
みなし訪問看護には、訪問看護ステーションのような新たな指定申請や専従看護師の配置が必要ないため、立ち上げ準備が簡略化できます。
また、設備や備品は運営母体である病院や診療所のものを利用できる可能性があり、現状の診療体制を活かして在宅医療に参入可能です。
人員や資金の確保が難しい医療機関でも、比較的始めやすいでしょう。
訪問看護ステーションの立ち上げに必要な要件について詳しくはこちら↓
訪問看護ステーションの立ち上げで必要なことは?手順や費用・助成金など解説
医師との連携が密
みなし訪問看護は病院や診療所に併設されており、主治医と看護師が日常的に連携しやすい点が強みです。
訪問先で利用者の体調の変化をすぐに医師へ報告して迅速な指示を受けられるため、質の高い在宅医療が提供できます。
患者にとっても、組織として連携体制が保証されていることは、非常に安心でしょう。
継続的な支援が可能
みなし訪問看護を利用すると、病院での治療から自宅での療養生活まで一貫して同じ医療機関で行えるため、医療内容の引き継ぎが簡単に行えます。
在宅療養でも主治医の治療方針を踏まえた看護の提供が可能です。患者との長期的な関係を築きやすく、継続的な収益にもつながります。
利用者を獲得しやすい
みなし訪問看護は、通院中や退院後の患者が対象となるため、利用者を獲得しやすいでしょう。
地域で広く利用者を募る必要がなく、安定した利用者確保が可能です。
広告や営業活動に大きなコストをかけずに利用者を集められるため、効率的な事業運営につながります。
みなし訪問看護のデメリット
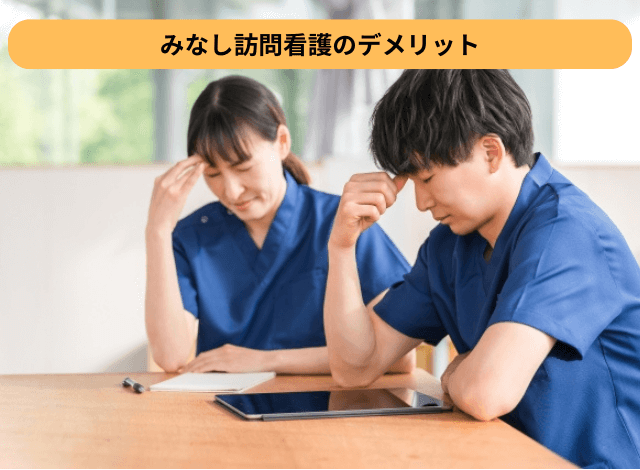
- 収益性が低く報酬が低い傾向にある
- サービス提供範囲が狭く総合的なスキルアップが難しい
みなし訪問看護のデメリットは、主に上記の2点です。それぞれ詳しくみていきましょう。
収益性が低く報酬が低い傾向にある
みなし訪問看護は、訪問看護ステーションに比べて基本報酬が低く設定されており、同じサービスを提供しても収益は少なくなりがちです。
また、利用者の対象が自院の患者に限られる点から、事業の拡大が難しい傾向にあります。
地域全体から幅広く利用者を受け入れられる訪問看護ステーションと比べると、初期投資は抑えられるものの、長期的にみると収益の伸びは限定的となります。
サービス提供範囲が狭く総合的なスキルアップが難しい
みなし訪問看護は、自院の診療科に関連する患者さんのみを対象とするため、提供できるサービスの範囲が限られます。
たとえば、訪問看護ステーションとは異なり、リハビリ専門職による施術を行ってもリハビリテーション報酬の請求はできません。
リハビリテーションサービスで報酬を請求する場合は、別途適切な施設基準を満たす必要があるからです。
そのため、理学療法士などの専門家が看護師に同行してリハビリテーションを実施しても、診療報酬は訪問看護費の請求のみとなります。
また、サービス対象者が運営する病院・診療所の診療科に関連する患者に限定されるため、提供できる看護の内容もその診療科の範囲に制約され、非常に限定的です。
特定の分野に特化できる一方で、多様な疾患や幅広いニーズに対応するスキルは向上しにくいでしょう。
みなし訪問看護の立ち上げ前に特徴を知っておこう
みなし訪問看護は、病院や診療所が自院の機能を活かして始められる仕組みです。
新たな指定申請が不要で、人員・設備・備品は既存のものが対応可能な場合もあるため、訪問看護ステーションよりも開業しやすいといえるでしょう。
「主治医との連携が密である」「外来や入院から在宅療養への移行をスムーズに行える」などの点から、医療内容の引き継ぎが密に行えて患者の安心感につながります。
一方で、基本報酬が低く、利用者が自院の患者に限られることなどから、事業拡大には限界があります。
また、提供できるサービスは診療科の範囲内にとどまり、看護師のスキルアップに制約が出やすい点にも注意が必要です。

カテゴリー|その他